課税売上割合によって消費税の計算の難易度が変わる
以下の内容は、課税売上高が5億円以下であることを前提にしております。
消費税の計算方法は大きく分けると「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つがありますが、今回は「原則課税方式」の話となります。
「原則課税方式」は課税売上割合が95%以上か、又は95%未満かで計算の難易度が大きく変わり、納付すべき消費税の額も大きく変わります。
「課税売上割合」とは、ざっくりいうと、
【算式】 課税売上割合=課税売上高/(課税売上高+非課税売上高)
一般的な例でいうと、
課税売上高は、「本業の売上」
非課税売上高は、「居住用マンションの賃貸収入」や「上場株式の売却代金の5%相当額」となります。
非課税売上高が増加すると分母が増加し、課税売上割合が小さくなります。
そして、課税売上割合が95%以上か未満で消費税の計算方法の難易度が変わります。
以下の算式をご覧ください。
⑴課税売上割合が95%以上の場合
➀全額控除方式
【算式】※計算式は単純
課税売上高に係る消費税△課税仕入に係る消費税(100%控除)=納める消費税
⑵課税売上割合が95%未満の場合
この場合には、「一括比例配分方式」と「個別対応方式」の選択適用となります。
➀一括比例配分方式 ※計算式は少し複雑
【算式】
課税売上高に係る消費税△課税仕入に係る消費税✕課税売上割合(部分的に控除)=納める消費税
②個別対応方式 ※計算式は複雑
【算式】
課税売上高に係る消費税△課税売上のみに係る課税仕入の消費税(100%控除)△課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入の消費税✕課税売上割合(部分的に控除)=納める消費税
となります。
一般的に納める消費税の金額が小さいものから順に
➀全額控除方式
②個別対応方式
③一括比例配分方式
となります。
課税売上割合が95%以上であれば、計算式の単純で、かつ、納める消費税が最も小さい「全額控除方式」を選択できますが、
課税売上割合が95%未満となった場合、納める消費税の金額を小さくおさえるために、多くが「一括比例配分方式」ではなく「個別対応方式」を選択することになります。
「個別対応方式」を選択した場合には、課税仕入れを取引ごとに
➀課税売上に係る課税仕入れ
②非課税売上に係る課税仕入れ
③課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ
に区分する必要があり、課税区分の判断が煩雑、かつ、慎重に判断することになります。
中小零細の法人が投資活動をすると、課税売上割合に大きく影響。
法人の活動は「営業活動」、「財務活動」、「投資活動」の3つに区分に分けることができます。
「営業活動」とは、主に本業の活動のこと。
「財務活動」とは、主に借入金による資金調達のこと。
そして、「投資活動」とは固定資産や株式、収益不動産などに対する投資を言います。
最近では、本業とは別に「投資活動」を積極的にする中小零細の法人も増えてきました。
そして「投資活動」の代表例が、前節で述べた「株式の売買」や「居住用マンションの賃貸収入」となります。
ここで注意が必要なのは「消費税」。
「株式の売買」や「居住用マンションの賃貸」の取引が多くなると、非課税売上高の金額が大きくなります。
非課税売上高が大きくなると、課税売上割合の分母が大きくなり、課税売上割合も小さくなります。
課税売上割合が95%未満となると、「一括比例配分方式」よりも「個別対応方式」のほうが納める消費税の金額は小さくなりますが、
「個別対応方式」の場合には、取引を「課税仕入」と「それ以外の取引(対象外取引、非課税取引など)」に区分し、
更に「課税仕入」を以下の3つに区分する必要があるので消費税の計算の難易度は難しくなります。
➀課税売上に係る課税仕入れ
②非課税売上に係る課税仕入れ
③課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ
消費税に強い税理士を探すには?
インボイス制度が施行されると同時に税理士の廃業が増加しました。
廃業理由は様々ですが、複雑化する消費税実務についていけないというのも理由のひとつです。
実は税理士でも消費税実務が得意な税理士とそうでない税理士がいます。
それでは消費税実務が得意な税理士をどうやって探せば良いのか?
探し方のヒントを3つご紹介しますね。
まず、一つ目。これが一番だと思いますが
⑴その税理士が、中小零細企業の税務顧問の経験が豊富であるか否か調べてみる、です。
大企業は、本業の売上が巨額であるため、財務活動をしたとしても課税売上割合が95%未満になる可能性が極めて小さく、課税売上割合が95%以上の全額控除方式が適用できるため、実は消費税計算はそこまで難しくはありません。
いっぽうで、中小零細企業はスモールビジネスで本業の売上もそこまで大きくないため、財務活動で「株式の売買」や「居住用マンションの賃貸収入」をして非課税売上高が増加した場合には、課税売上割合がと95%未満になりやすく、個別対応方式で計算をする機会が多くなります。
つまり、中小零細企業の税務顧問の経験が豊富であると、個別対応方式の経験もそれなりに積んでる可能性が高いです。
次に2つ目。
⑵その税理士が、消費税関連の講師のセミナーに経験、ホームページやブログ、You tubeなどで情報発信をしている
セミナーの講師をするにしろ、ホームページやブログで情報発信するにしろ、そのテーマについて勉強する必要があります。私もインボイス制度のセミナー講師した経験がありますが、受講者から受ける質問も想定してかなり勉強しました。ホームページやブログで情報発信する場合にも同様に勉強する必要があります。
あとは、その税理士の消費税業務のメニュー価格表も調べてみると良いとも思います。
そのメニュー価格表が
➀2割特例、簡易課税制度
➁全額控除 、一括比例配分方式
③個別対応方式
の3つに区分されているかです。
実は区分ごとに消費税業務の業務量が大きく異なります。(業務量は➀<➁<③)
個別対応方式の経験がある税理士ほどそれぞれの業務量の違いを身をもって経験しているため、その経験がメニュー表に反映されている可能性は高いです。
最後に3つ目。
⑶その税理士が、税理士試験の「消費税法」に合格しているかです。
税理士試験の税法科目は、1科目ごとの学習内容はかなり深いです。
その税法の個々の論点や法体系を理解し、条文を暗記する必要があります。
そして上記の勉強をして、本試験で上位10%に入ってようやく「合格」を手にすることになります。
「消費税法」に合格したということは、少なくとも「知識」においては消費税法に精通している証となります。
税務は「知識」と「実務経験」の両方が必要となる仕事です。
個人的には⑴→⑵→⑶の順番で、税理士を調べてみてはいかがでしょうか?
ネットで検索したり、実際に税理士に会って話をして⑴〜⑶の内容を確認するのが良いかと。
良ければ参考にしてくださいね。
-編集後記-
先週末は実家の畑を手伝いました。
畑に植えられている桜が開花しているよう。
ところどころ、桜も咲いてきましたね。
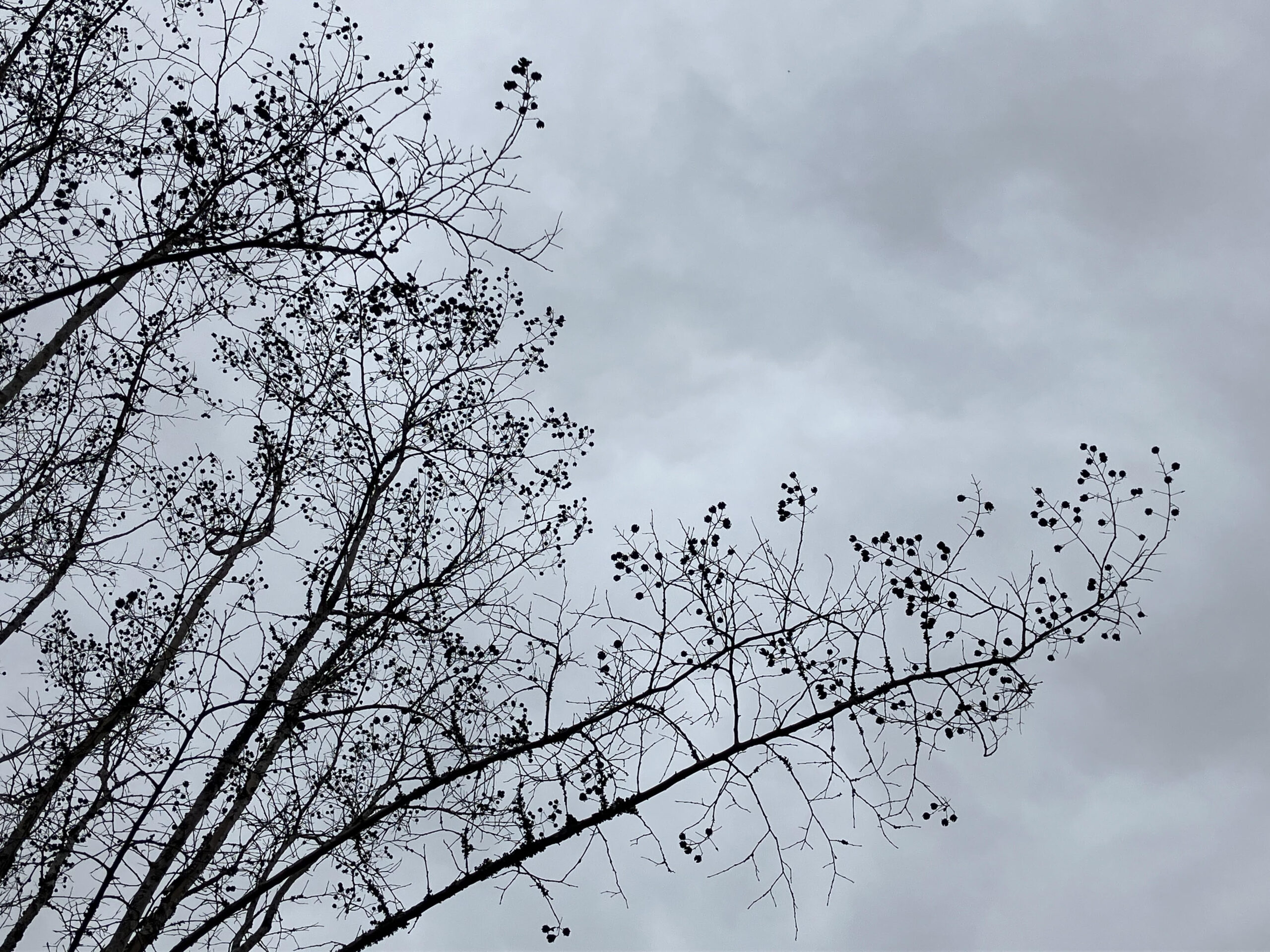











にお あつし
こんにちは!
マラソン・バイク・フルートをこよなく愛する
京都府長岡京市在住の税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。
今回は、“消費税に強い税理士、についてです。