インボイス制度の準備を着々と進める
10月1日に施行されるインボイス制度に向けて顧問先さまごとに準備を着々と進めています。
先行して進めるべき項目は
➀適格請求書発行事業者の登録申請書の提出
②登録番号の入手
③自社発行の請求書の記載方法のレクチャー
➃消費税の経費(仕入税額控除)の計算方法(原則課税方式又は簡易課税方式)の選択
⑤原則課税方式を選択した顧問先に対しては、仕入先等の登録番号の収集と会計システム(IT)の活用方法の提案
など
私の顧問先さまの多くは➀~③までは完了し、➃~⑤を現在進行形で進めています。
ただし、先行して上記の項目を進めていたとしても、インボイス制度施行後の原則課税の消費税実務を想像すると、従来よりも実務がかなり煩雑になる予想されます。
そのため、顧問先さまごと、特に原則課税で消費税を計算する顧問先さまのために例年よりも多くの工数(時間)を見積り計画をたてています。
これを機に仕事や生活の習慣を見直そう
最近だとコロナを期に事務所勤務から在宅勤務、勤務から独立など、働き方や生き方が変わりました。
インボイス制度の導入も、事業主さまや税理士にとっては国から難題を突きつけられた訳ですが、こういうインパクトのある事象の変化のときは、何か(特に習慣)を変える良い機会かなと思います。
私が最近実践したこと、小さなことではありますが、
・BGM代わりにYou tubeやテレビをダラダラつけて仕事をしない。目の前の1つ課題(仕事)に対する集中力を鍛える。
・夏でも冬でも快適な室温で仕事をしたいのでサーキュレーターの購入して空気の循環をはかる
・郵便局に行く時間がもったいないため、紙でのやりとりを削減し電子データでのやりとりを増やした
・お客さまの申告書控えや調書は紙での保管はせず電子化して、必要なときに瞬時に取り出せる体制を整えた
などです。
効率化できることは効率化して「時間」を生み出し、その時間に余裕のある状態で顧問先さまの消費税実務や自分のプライベートに充てたいと考えています。
インボイス制度の施行まで残り3ヶ月。
それまでに効率できるものは効率化しようと思います。
インボイスの対応で評価が二分されると予想
消費税の計算が原則課税の顧問先さまについては、何の準備もせずにインボイス制度の施行を迎えると、施行後の消費税実務が超煩雑になり、最悪の場合、多くの取引の仕入税額控除が80%相当の状態で申告せざるを得ない状態に陥いる可能性も生じます。
そのような状態に陥った場合、顧問先さまからの税理士に対しての評価は低くなります。
ただし、インボイス制度は税理士だけの力で対応できるものではなく、特に仕入先等の登録番号の収集等や会計システムへの登録については顧問先さまに主導で動いて頂く必要があります。
そのためには、
・顧問先さまにインボイス制度の概要を理解して頂く
・インボイス制度施行後の納める消費税のシミュレーションと納付額をおさえるための対策方法を伝える。(優越的地位の濫用や下請法の概要も説明)
・特に仕入先等の登録番号の収集等の大切さやインボイスに関する会計システムの操作方法を伝える
など、税理士側も積極的に動く必要があります。
インボイス制度施行後も「丹尾さんが顧問税理士で良かった」と言っていただけるように、事前に積極的に動いていこうと思います。
■編集後記
午前中は決算・申告業務
午後からクライアント訪問。

1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒製造(フォークリフトマン&夜勤塗装)⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら









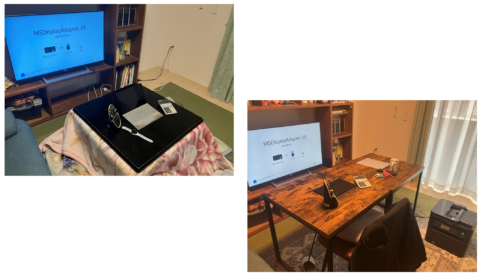


■相続・贈与・譲渡などの資産税サービス
■事業承継サービス
■会計・税務サービス
■税務調査・無申告対応サービス
■税務相談サービス
■「丹尾 淳史(にお あつし)」ってどんな税理士なの?